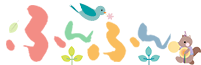ふんふん古事記30「雉の頓使(ひたづかい)」
葦原中国(あしはらのなかつくに)に使いに行った天菩比神(あめのほひのかみ)が三年過ぎても帰ってこないので、天照大御神は、高御産巣日神をはじめ諸々の神様に集まってもらい相談しました。「次にどの神を使わそうか」という問いに、思金神(おもいかねのかみ)がいいました。
「天津国の玉神の子の天若日子(あめのわかひこ)を遣わすことになりました。弓(天之波士弓)と矢(天之加久矢)を賜わって葦原中国に降り立った天若日子は、大国主神の娘の下照比売(したでるひめ)と結婚し、この国を我がものにしようと企むようになり、また八年の歳月が流れました。
いよいよ困った天照大御神と高御産巣日神はまた、神々を集めました。
「天若日子は八年も帰ってこない。その訳を聞きにどの神を遣わせばよいのか」
思金神は「鳴女(なきめ=雉のこと)を遣わすべきです」と答えました。鳴女は、天から降り天若日子の家の前の湯津楓(ゆつかつら=モクセイ?)の木にとまり、天つ神から預かった詔(みことのり)を正確に伝えたのです。
鳴女の言葉を聞いた天佐具売(あめのさぐめ=秘密を探る巫女)は、これを凶と判断、「この鳥は、鳴き声がよくないから射殺すべき」と扇動しました。天若日子は、天つ神から賜った弓と矢で、鳴女を射殺してしまいました。雉の胸を貫通した矢は空に舞い上がり天の安の河の河原に居られた天照大御神と高御産巣日神の所に飛んでいきました。
高御産巣日神は血の付いた矢が天若日子に授けた矢であることが分かりました。
「もし天若日子が命令に背かず。悪しき神を射た矢が届いたのならば、天若日子に当たるのではないぞ。もし邪心があるなら、天若日子よ。この屋に当たって死に至るであろう」
こういうと、矢を手に取り、矢が通ってきた穴から衝き返し下されたのです。矢は寝ていた天若日子の胸に当たって死をもたらしました。鳴女は帰りませんでした。「雉の頓使」行ったきり帰ってこない使者という諺はここから生まれました。